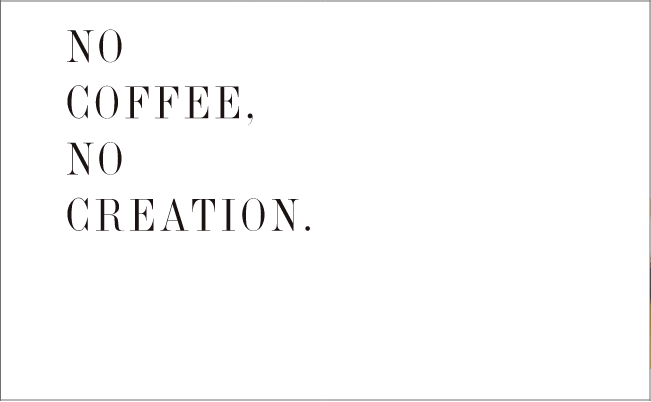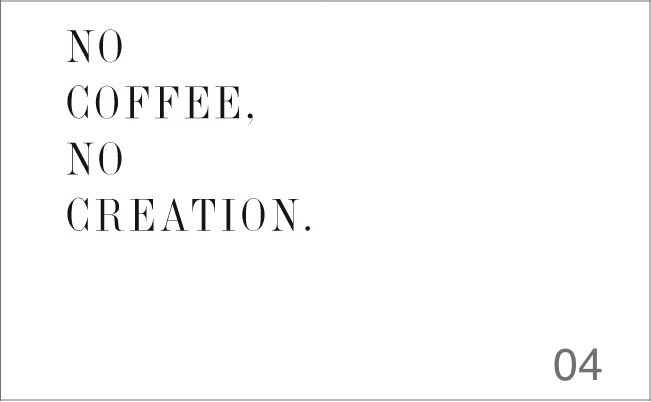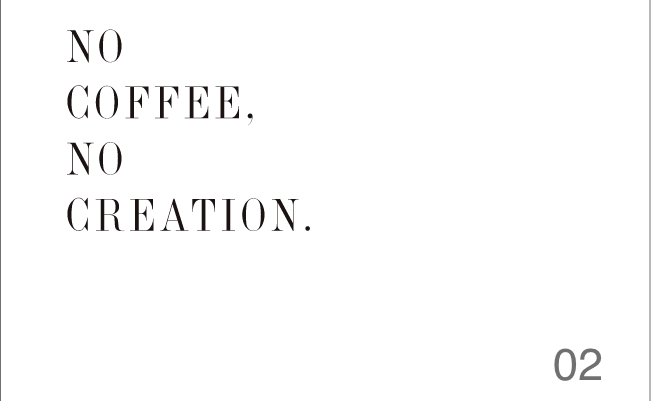NO COFFEE. NO CREATION.
寺田寅彦『コーヒー哲学序説』
- 一杯のコーヒーから哲学へ
-
オランダ宣教師たちによって日本にコーヒーがもたらされたのは17世紀ほど、 それらが開国を機に庶民へと普及したのは江戸末期から明治以降になります。 「新しい飲料」としてのコーヒーを口にした日本人は、どのようなことを考えたのでしょうか? 明治時代に物理学者・随筆家として活躍した寺田寅彦は、師である夏目漱石にも認められた文学の才能と、 持ち前の科学的洞察を活かして、優れたエッセイを数多く生み出しました。 彼は相当なコーヒー通だったようで、『コーヒー哲学序説』というコーヒーにまつわる随筆を残しています。 寺田寅彦のはじめて口にしたコーヒーは、嗜好飲料ではありませんでした。 彼の幼少期、体の弱い人への薬として出された牛乳の、美味とは言えない味を緩和するため、医者がコーヒーの粉を混ぜたのだといいます。 けれどもその粉のエキゾチックな味と香りに、幼少の寺田寅彦は心酔してしまったようです。
-

その後、ベルリン留学時の体験などを通して、寺田寅彦はコーヒーへの愛着を深めていきました。 帰国後も喫茶店をめぐり、コーヒーを飲む習慣は続きます。 彼は自分を「コーヒー通ではない」としながらも、店によってコーヒーの味に区別があることに思いを馳せ、 「コーヒーの出し方はたしかに一つの芸術である」と言います。 寺田寅彦はまた、「コーヒーを飲むためにコーヒーを飲むのではない」とも記しています。 自宅で苦労してコーヒーを淹れても、「何か物足りない」と言うのです。 いわく、コーヒーの味は「コーヒーによって呼び出される幻想曲の味」であり、それを呼び出すには「前奏が必要」なのだそう。 どうやら彼は、コーヒーを飲むことを単なる行為としてではなく、喫茶店の雰囲気やシチュエーションを含めた、総合的な体験としてとらえていたようです。 『コーヒー哲学序説』はそれから、哲学・文化とコーヒーとの関係へと話が広がっていきます。 短いながらも寺田寅彦の思索をたどれる名作です。ぜひ今日の一杯をお供に読んでみてください。
NO COFFEE. NO CREATION.
トピックス別
メールマガジンの新規登録または配信停止はこちらのフォームから。